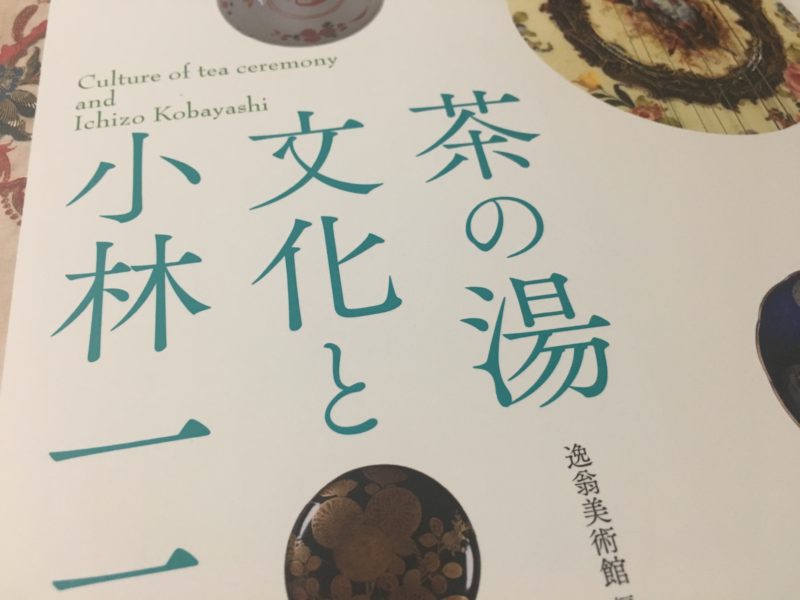先日、大阪府池田市にある「逸翁(いつおう)美術館」に行ってきました。
逸翁美術館は、阪急電鉄、宝塚歌劇団、阪急百貨店、東宝などを創業した、小林一三氏(こばやしいちぞう、以下敬称略)が集めた美術品を所蔵する美術館です。
一三は、茶の湯をこよなく愛した人で、多くの茶道具を収集しています。
「逸翁」は、一三の「号」です。「号」とは、文人、画家などが本名以外につける名前のことで、称号の略かと思います。いわゆる「雅号(がごう)」を指して「号」という時もあるかも知れません。
(この辺りの正確なことはわかりませぬ。)

織部四方鉢 桃山時代(思文閣出版「茶の湯文化と小林一三」逸翁美術館編)
ところで、茶人・一三の話をする前に、まずは事業家としての一三について触れたいと思います。
一三は、鉄道開発とともに宅地開発を行って大成功した世界で最初の事業家です。
阪急電鉄(当時は箕面有馬電機軌道)を設立した頃、都市と都市を結ぶ鉄道は存在していましたが、一三は、まだ開発されていない場所に鉄道を敷き、その沿線に生活圏を作って人を呼び込むことも同時に行ったのです。
当時、マイホームというのは資産家など一部の層に限られていました。
そんな時代に、「頭金として売値の2割、残りを10年間月賦で払い込むと住宅の所有権を移転させる」という、土地・住宅を担保とした現在の住宅ローンの原型とも言える住宅販売方法を提案したのが一三でした。
お陰で、普通のサラリーマンも「マイホームを持つ」ということが珍しくなくなっていったんですね。
また、一三は、鉄道と住宅地を作っただけではありません。生活は楽しくなければならないとして、エンターテイメントの分野にも進出し「生活文化」をも創り出しました。
大阪梅田の阪急百貨店は、世界最初の駅直結のターミナルデパートでした。宝塚歌劇団や東宝グループの成功も私たちのよく知るところです。
今でこそ、鉄道インフラと、宅地や娯楽施設などを合わせて開発するのが当たり前になっていますが、そもそも、こういったスタイルは一三が確立したものだったんですね。
しかも、一三はただ自分さえ成功すれば良いというような人ではなかったようです。
小売店への本格進出となった阪急百貨店の経営では、「良い品を安く売る」ことを目指したとはいえ、何でもかんでも薄利多売をしたのでは、周辺の小売店の経営へ大きな影響が出てしまうこと懸念しました。
そこで、一三は、百貨店が価格面で競争する場合は「自分の手で、自分の工夫で、自分の設備で製造した商品に限るべき」という方針を持って百貨店経営を進めていったと言われます。
うーん、懐の深い経営者です。
さて、前置き長くなりましたが、一三は「3度の飯より茶の湯が好き」だったのではないかと思われるほどの茶人でもありました。
この写真は、茶花を活けるところでしょうか。キマっています。

一三のように、明治から昭和にかけて、インフラ業など大事業で成功し、政治の世界にも関わり、巨万の富を築いた人たちの中には、その財力を使って茶道具を購入し、自ら茶の湯を楽しんでいた人たちがいました。
このような人たちを、お茶の世界では「近代数寄者」と呼んでいます。
「数寄者(すきしゃ)」とは、職業として茶道を教える茶人と区別する意味で使われる言葉です。
なかなか定義付けの難しい言葉ですが、財界、政界、法曹界、あるいは医者など、飛び抜けた財力をもって、多くの茶道具を収集し、自らの生活の中でも茶の湯に傾倒する人々を数寄者と呼んでいるようです。
たとえば、一三の他に、財界の近代数寄者というと、絹貿易で富を築いた横浜の原富太郎(三渓)、三井物産の益田孝(鈍翁)、東武鉄道の根津嘉一郎(青山)、荏原製作所の畠山一清(即翁)、電力王と言われた松永安左ヱ門(耳庵)、などが有名です。
※カッコ内は号
明治、大正、昭和にかけては、日本が近代化を成し遂げ、財閥制度も存在していた時代でしたから、華やかな近代数寄者の歴史があったのだと思います。
もっとも、お金持ちで茶の湯が好きで、というだけでなく、この時代の数寄者の特徴は、驚くべき教養人でもあったことです。
一三も、元々の興味は茶の湯にあったのではなく、学生時代には小説を描き、演劇に夢中で、文芸に対する興味が先行していました。与謝蕪村が好きで、蕪村そっくりの書画を残し、やがて日本有数の蕪村コレクターになります。
小説家は諦め、事業家として成功しても、漢文、仏教、能、歌舞伎など芸能への理解を深め、和歌、俳諧を学び、和文化だけでなく、東洋・西洋の文化にも精通する国際性もありました。
このようなことは、一三だけのことではなく、近代の数寄者に共通する点で、茶の湯以外の幅広い教養と興味から日本美術の世界に入り、結果、その中核にある茶の湯にたどり着いたという人が多いと言われます。
茶の湯・茶道が総合芸術だと言われるのも頷ける気がします。。。
ところで、数寄者の中でも、一三は特に自由な発想をもっていた人のようです。
茶会をもっと身近なものにしようと、懐石料理ではなく、西洋料理や玉子丼、カレーライスを出したこともあったとか。
型があるのが茶道と思われがちですが、型に「捉われない」ことが茶道の本旨です。
一三は、「利休、遠州くそ喰らえのお茶を試みてほしい」とその著書で語っているぐらいなので、その時代の茶道界を批判もし、色々なことを試みていたようです。
(カレーライスはちょっと匂いが強すぎるのではと思いますが・・・)
また、一三は、外国から仕入れてきたガレやドームの器を、積極的に茶道具に見立てることもしました。

思文閣出版「茶の湯文化と小林一三」逸翁美術館編より
このように、茶道具でないものを茶道具として利用することを「見立て」と言いますが、一三のこのようなセンスは、見る人を楽しませるものですし、また、勉強にもなります。
こちらは、一三が考案した茶室の一つ「即庵」です。お客は皆、椅子に座ることができるんですね。

茶道人口は、一三の生きていた時代よりもかなり少なくなってしまいました。
このような茶道界の現在を、一三はすでに当時から予見し、憂いて、「これからの時代に茶の湯はいかにあるべきか」を真剣に問いかける数寄者だったといいます。
このような一三の問題意識は、1952年に出版された著書「新茶道」に記されているそうなので、これからこの本を読んでみるつもりです。
何事も、時代とともに変化していく柔軟性は必要だと思いますが、時代を経ても変わらないことに意味がある場合もあると思います。
65年前に書かれたこの書籍に、私自身がどう影響されるか、楽しみです。